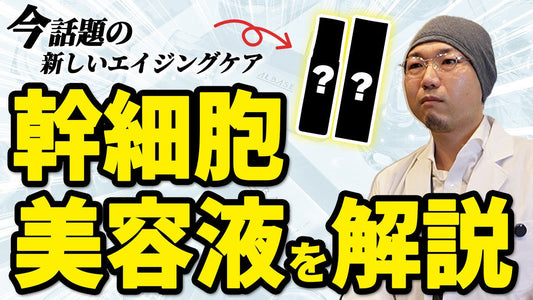ストレスの生物学的本質から導かれる対処法ーストレス対処法1ー
アルベイズ梶原Share

こんにちは
アルベイズ梶原です。
入試本番直前なこともあって、お勉強コンテンツが続きます。
以前の記事と内容的にかぶる部分もありますが、ストレスの生物学的な本質について解説していきます。
ストレスが生じる根源的な原因がわかってくると、対処法についてもかなり理解できるようになります。
ストレス反応は天敵に備えるための機能
脳の三層構造とストレスの関係でも解説しましたが、生物の脳は段階を踏んで進化してきています。
1.最も原始的な脳⇒脳幹(爬虫類脳)
2.古い大脳⇒大脳辺縁系(動物脳)
3.新しい大脳⇒大脳新皮質(人間脳)
の順番で形成されてきました。
このうちストレス反応と呼ばれる生体反応を起こしているのは、主に大脳辺縁系です。
実はストレス反応は元々、生物が生き残るために作り出したシステムです。
人間の祖先がまだ魚だったころにこのシステムは生まれました。
このシステムの中心になっているのが、大脳辺縁系の中でも扁桃体と呼ばれる場所です。
ちなみに扁桃体は魚の脳にも見られる部位です。
人間は現代でこそ、突然天敵から襲われるようなことはないですが、太古の昔、人間の祖先は常に天敵に襲われる危険に晒されていました。
この天敵に備えるためのシステムこそがストレス反応です。
扁桃体のお仕事
扁桃体は主に、情報の重要性を判断しています。
手順としては
情報⇒扁桃体⇒記憶を参照⇒危険かどうかを判断
という順番です。
例えば、いつも例として登場してもらっているライオンが目の前にいるとしましょう。
まずは視覚を通して、「目の前にライオンがいる」という情報が脳に送られます。
その情報を扁桃体が受け取ると、脳に保管されているライオンに関連している記憶を参照します。
「目の前のライオン」と「記憶のライオン」を照合するわけですね。
で、
記憶の中に「ライオンに襲われた」という経験があった場合、扁桃体は「今、目の前にいるライオンは襲いかかってくるかもしれない。危険だ」と判断します。
わかりやすいように簡略化していますが、目の前にライオンが現れた時このような情報処理が脳内では行われています。
こういった膨大な情報処理が脳内では一瞬で行われているわけです。
扁桃体が危険だと判断すると、脳下垂体から副腎皮質刺激ホルモンを分泌し、それが副腎に到達すると副腎皮質ホルモン(コルチゾール)が分泌されます。
副腎皮質ホルモンというのは、いわゆるストレスホルモンです。
このストレスホルモンが全身に働きかけることで、ストレス反応を起こします。
また、交感神経が優位になり、体はFight or Flightモードに入ります。
緊張で頭が真っ白になるのは闘争逃走反応のせい
天敵と運悪く出会ってしまった場合、生き残るために取るべき手段は2つしかありません。
つまり、
逃げるか?
戦うか?
のどちらかです。
大脳辺縁系を持つ生物では、天敵を見つける(=強いストレスを受ける)とストレスホルモンの働きによって、体が「戦うか?逃げるか?」に最適化されます。
もちろん、人間も大脳辺縁系を持っていますので、例外ではありません。
これが最も代表的なストレス反応、闘争逃走反応(Fight or Flight Response)です。
闘争逃走反応が起こると、体には以下のような反応が起こります。
・大脳新皮質の活動が抑制される
大脳新皮質は高度な思考ができますが、天敵に襲われるような瞬間的な反応が求められる状況には向いていません。
こういった直感的な判断は大脳辺縁系が行います。
(一説によると大脳辺縁系は大脳新皮質の20万倍の速度で情報を処理できると言われています)
「今、目の前にライオンがいるけど、ここはじっくりとライオンの生態を分析した上で、理性的に逃げるか戦うかを判断しよう」
なんて悠長に考えていたら、考えている間に食べられてしまいますから(^_^;)
大脳辺縁系が行った判断を大脳新皮質に邪魔されないように、ストレスホルモンが大脳新皮質の活動を抑えるのです。
ちなみに、緊張した時に頭が真っ白になるのは、ストレスホルモンによって大脳新皮質の活動が抑え込まれるためです。
・血圧や脈拍が上昇し、呼吸が早くなる
天敵に出会ってしまった場合、全力で戦うか全力で逃げるか、どちらかしかありません。
どちらにしても、素早くそして力強く体を動かす必要があります。
そのために、血圧が上がり、筋肉への血流が増え、筋肉にエネルギーを供給します。
また、筋肉を動かすために酸素も必要になるので、呼吸が早くなります。
運転中に対向車が中央線を超えてこちらに向かってくるなど、危ない目に会うと心臓がバクバクして呼吸が早くなりますが、その反応を引き起こしているのはストレスホルモンなんですね。
(僕はこの状況に遭遇したことが一度だけあります。なんとか避けたのでぶつからずに済みましたが、あの時は本気で死ぬかと思いました・・・)
・血が固まりやすくなる
これは血小板が増えるためです。
敵に襲われているということは、いつ怪我をして出血するかわかりません。
万が一、怪我をしてもすぐに出血が止まるように血が固まりやすくなるというわけです。
・表皮の血流が抑制される
上と同様に出血を抑えるために表皮の血流は抑制されます。
・血糖値・血中脂肪の上昇
闘争逃走反応が起こると肝臓が糖や脂肪を血中へ放出します。
もちろん、これも筋肉に闘争(逃走)のためのエネルギーを供給するためです。
・免疫系が抑制される
免疫系は主にウィルス・細菌などの侵入者や、がん細胞と戦うための仕組みです。
しかし、目の前にライオンがいるのにウィルスのことなんて気にしている場合じゃないですよね?
それどころじゃねぇ!って話なので。
したがって、免疫系に回されていたエネルギーはカットされて闘争(逃走)に回されます。
・消化器や生殖器への血流が減る
これも理屈は同じで、敵がすぐそこにいるのに消化や生殖にエネルギーを回している場合じゃないからです。
ちなみに、「男は緊張しすぎると勃たない」とよく言われますが、これはこの闘争・逃走反応のせいです。
と、こんな具合に、体は闘争(逃走)に最適化されます。
一覧でまとめておきます。
・大脳新皮質の活動が抑制される
・血圧や脈拍が上昇し、呼吸が早くなる
・血が固まりやすくなる
・血糖値・血中脂肪の上昇
・免疫系が抑制される
・消化器や生殖器への血流が減る
これが闘争逃走反応のときに起こる体の変化です。
緊張した時に、頭が真っ白になるとか、心臓がドキドキして息が苦しくなるなどは、ほとんどの人が経験したことあるのではないかと思います。
アレがまさに太古の昔から残っている闘争逃走反応です。
扁桃体は危険ものだけでなく「新しいもの」にも反応する
ちなみに、扁桃体は危険なものだけでなく「新しいもの」を見つけた時にも強く反応します。
「新しいもの」つまり、記憶に無いものです。
記憶にないのでそれは危険なのか安全なのか判断のしようがないんですが、もしかすると危険かもしれないので、とりあえず警戒しておけという風に判断するわけですね。
ちなみに、知らない人に囲まれているとストレスを感じますが、それはこのような扁桃体の特性が原因です。
知らない人は安全かどうかわからないから、とりあえず警戒する、という風に人間の脳はできています。
逆に、知っていてかつそれが安全だと記憶されていれば、ストレス反応は起こりません。
「この人はいつも良くしてくれているお隣の鈴木さんだ」と大脳辺縁系が判断すれば、特にストレス反応を起こす必要はないわけですね。
まとめ
今回の内容をまとめておきましょう。
・ストレス反応は敵から生き残るために生まれた
・ストレス反応は主に大脳辺縁系の働きで起こる
・ストレスホルモンが闘争逃走反応を起こす
というあたりですね。
さて、ここまでの話ではストレス反応は単に天敵から逃げるためのシステムで、全然悪いものではないですよね?
しかし、「ストレス反応が起こりっぱなし」の状態になると、いろんな問題が生じてきます。
そのお話はまた今度。
余談:魚のうつ病
魚も慢性的に扁桃体が活性化されているとうつ病のような症状が出ます。
グッピーをその捕食者と一緒に飼育するという実験がありまして、
中央に透明な仕切りのある水槽の右にグッピー、左に捕食者という感じで分けて飼育します。
仕切りがあるのでグッピーは食べられることはないのですが、自然界であれば、間違いなく捕食される状況なので、グッピーの脳では扁桃体が活性化してストレス反応が起こります。
その状態のまま飼育するとグッピーは水槽の隅から動かなくなったそうです。