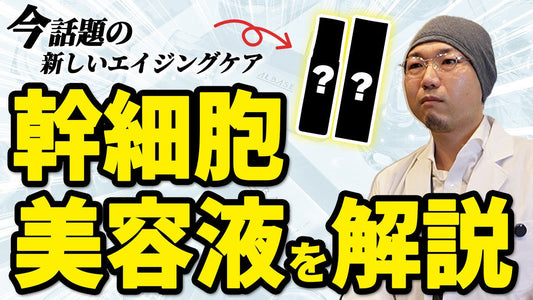脳の三層構造とストレスの関係
アルベイズ梶原Share

こんにちは
アルベイズ梶原です。
お勉強のついでに作った感あふれるガッツリ生物学な記事になっております。
今回は人間の神経系と脳の構造についてです。
人間がなぜ不安を感じるのか?とか
不安を感じるときに体にはどのような変化があるのか?とか
そういう部分を解説するにあたって、人間の神経系がどうなってるのかを解説しておいた方が良いと思いまして。
僕はこういう全体像みたいなものを把握できたほうがわかりやすいんですが、みなさんはどうでしょうか?
覚えておく必要はないので、ストレス関連の記事を読んでいてわからなくなったらこのページを見返してみてください。
人間の神経系
まずは神経系の全体図です。
まず人間の神経系はざっくり2つの系統にわかれます。
・中枢神経
・末梢神経
の2つです。
中枢神経は脳や脊髄、末梢神経はそれ以外の体の末梢に張り巡らされた神経を指します。
中枢神経はコンピューターでいうとCPUにあたります。
人間は外部から刺激があると、
末梢神経から入力された情報を中枢神経系に送り(インプット)、
その刺激に対してどのような反応をするかを決定して(情報処理)、
その信号を再び末梢神経に送る(アウトプット)
という動きをします。
「インプット⇒情報処理⇒アウトプット」という順番はコンピューターとまさに同じです。
例えば、熱々の鍋をつついている時、うっかり鍋のフチに腕が当たって、慌てて手を引っ込める反応を考えてみましょう。
この反応を、スローモーションで見ると
感覚神経が腕が熱いという信号を中枢神経に送る(インプット)
中枢神経はそのままだと火傷しそうだと判断し、腕を引っ込めるように指令をだす(情報処理)
運動神経が信号を送り、腕が引っ込む(アウトプット)
という感じになります。
実際は一瞬でこの「インプット⇒情報処理⇒アウトプット」という作業が行われています。
脳についてはまたあとで詳しく見るとして、まずは末梢神経を見ていきましょう。
末梢神経
末梢神経は
・体性神経
・自律神経
2つに分類されます。
体性神経は外部から中枢への情報入力、また筋肉など器官への中枢からの出力を担っています。
自律神経は意識とは無関係に動く器官(心拍、消化管運動、体温調節など)を制御する神経です。
体性神経
体性神経は
・感覚神経
・運動神経
の2つがあって、
感覚神経は「視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚」などのいわゆる五感を脳に伝えるための神経で、運動神経は筋肉に信号を送って動かすための神経です。
感覚神経がインプット、運動神経がアウトプットの役割を担っています。
自律神経
自律神経は
・交感神経
・副交感神経
の2つに分類されます。
この2つはみなさんもよく聞いたことがあると思います。
起きている時や興奮しているときは交感神経が優位に、
寝ているときやリラックスしているときは副交感神経が優位に
なります。
どっちが大事というものではなく、この2つが協調して体をコントロールしています。
つまりバランスが取れていることが大事です。
交感神経系が優位になっている時は行動的になり、集中力が高まり、食わてて消費カロリーが増えます。
体は休まらないので、疲れます。
交感神経系が強く活性化されている状態は”Fight or Flight”状態と呼ばれています。
眼の前に敵がいて、生き残るには戦うか逃げるかしかない状況に対応した自律神経系の状態です。
一方、副交感神経が優位になっているときは、リラックスして体を回復させている時です。
消化活動が活発になり、積極的にエネルギーを作り、消耗した体を回復させます。
食後、眠くなったりするのは消化のために副交感神経が優位になるからだと考えられています。
脳の3層構造
人間の脳は解剖学的には
・大脳
・間脳
・脳幹
・小脳
の4つに分けられます。
しかし、脳は生物の進化に従って、3段階で拡大してきているので、次の様に分けるとわかりやすいです。
・脳幹(爬虫類脳)
・大脳辺縁系(動物脳)
・大脳新皮質(人間脳)
の3つです。
進化が進むにつれて、
脳幹⇒大脳辺縁系⇒大脳新皮質
の順番で形成されて行っているので、位置としても脳幹が一番中心、その外に大脳辺縁系、一番外側に大脳新皮質という順番になっています。
生命維持における重要度も同じ順番で、心拍や呼吸を制御している爬虫類脳が機能停止すると、それは脳死となります。
逆に大脳新皮質は多少損傷しても生命維持には問題がありません。
実際、僕も前頭葉(大脳新皮質)の右側は腫瘍と一緒にかなり削っていますが、こうやってブログを書くことができています。
脳幹(爬虫類脳)
爬虫類など原始的な脊椎動物にも見られる脳で、最も原始的な脳。
脊椎動物の脳にはすべてこの部位があります。
人間で言うと、延髄、橋、間脳、中脳、などがこの爬虫類脳にあたリます。
呼吸や心拍、体温の調節など、生命維持に不可欠なはたらきをしている部位で、活動が停止すると医学的には脳死状態となります。
大脳辺縁系(動物脳)
大脳のうち内側にある古い脳で
・性欲や食欲など本能的な衝動
・喜怒哀楽などの感情
・自律神経の調節
・各種ホルモンの分泌
などに関わっています。
ホルモンの分泌や自律神経を通して体を制御しているのがこの大脳辺縁系です。
大脳新皮質(人間)
大脳のうち外側にあるもっとも新しい脳。
ホモ・サピエンス(人間)だけが、高度に発達した大脳新皮質を持ち、理性や言語など、人間だけが使える高度な脳機能を担っています。
扁桃体と海馬
大脳辺縁系の中で特に重要になる部位が扁桃体と海馬です。
ストレスの話ではたびたび登場すると思うので、紹介しておきます。
扁桃体
- 恐怖や、不安、悲しみ、喜びなどの感情を司る部位
- 外部からの刺激が生命活動にとって有益か有害かを判断する
- 恐怖や不安を感じる際に活発に活動する
-
うつ病患者では肥大し、過剰に活動している

海馬
- 短期記憶を行う
- 扁桃体と協調して情報の重要度判断を行い、重要度の高いは長期記憶として保存する
-
アルツハイマー病やうつ病で萎縮することが知られている
まとめ
脳の構造と機能についてまとめて来ましたが、いかがだったでしょうか?
今回は純粋なお勉強コンテンツなので、特に面白いことはないと思いますが、ストレス関連の話で登場してしまう用語なので、まとめておきました。
余談:脳のことは良くわかっていない
脳の機能については、人体の中でも特に未解明のことが多いです。
短期記憶を海馬が行っていることは分かっていますが、長期記憶がどうやって行われているかはほとんど分かっていません。
脳外科の手術はデフォルトで10時間とか手術時間が長いんですが、執刀してくれた先生に聞いたところによると、
脳外科の手術はほとんどの時間、その箇所が切って大丈夫かの確認をしている
とのことでした。
その箇所がどういう機能を担っているかは見ても分からないので、その箇所の機能を一時停止してみて、手足の電気信号を確認して問題がなければ、切ってOK
みたいなことを延々10時間繰り返しているそうです。
同じ機能でも人によって担っている脳の部位が全然、違ってることも多く、
一般的に、言語野は左脳にあることが多い(僕もこのタイプでした)のですが、人によっては言語野が右脳にあることもあります。
言語野が右脳の人の場合、僕のように右脳に腫瘍ができると、言語機能が障害されて、言葉が理解できなくなったり、話せなくなったりします。
こういう患者さんの場合、手術中に起こして、お話しながら手術を進めるらしいです。
脳の一部の機能を停止させて、それで文字を読めなくなったり話せなくなったりしたら、その箇所は言語機能を担っているので、切れないと判断する。
一昔前はとにかく患者を生かすのが重要だと考えられていたので、脳の機能は無視して取れる腫瘍は全部取るという手術が一般的だったらしいですが、それだと患者は廃人同然になってしまうので、現在は腫瘍を取ることよりも脳の機能を残すことを重視する手術が主流です。