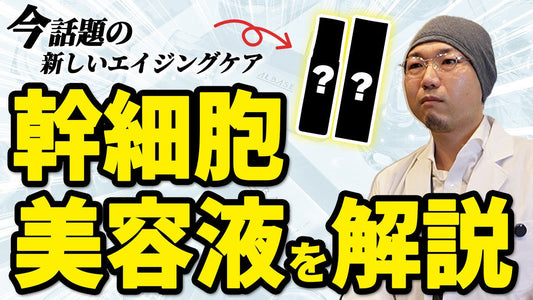現代医学が無視してきた事実と古典医学が重視してきた本質ー新健康観4ー
アルベイズ梶原Share

こんにりは
アルベイズ梶原です。
新健康観シリーズ4回目です。
今回は古典医療の具体例として僕も現在進行系で勉強中のアーユルヴェーダについて解説していきます。
まだ勉強中なので、おかしなところや間違っているところもあるかもしれませんので、参考程度にとどめておいてください。
前回は呪術と医術の関係についてお話しました。
アーユルヴェーダの教え
5000年ほど前に現在のインドで体系化された医学体系です。
現代医学的には意味不明なことも少なくないですが、現代医学では治せない病気がアーユルヴェーダの治療で治ってしまう例もあります。
ちなみに本場インドでは現在もアーユルヴェーダは医療として西洋医学と組み合わせて使われたりしています。
日本でいう消化器内科、外科のようにアーユルヴェーダ科みたいなものがあるらしいです。
ヒトは何からできている?
科学的には水とタンパク質と脂質ということになりますが、
- 身体
- 心
- 魂
の3つが、アユールベーダにおける人間の構成要素です
体(物質)と心(心理)までは現代医学もそれなりに知見がありますが、魂に関しては完全に無知です。
そもそも科学的な分析の対象とすらしていなかった要素です。
アーユルヴェーダの美容
「外見には中身が反映されている」とアーユルヴェーダでは考えるので「美容=健康」
です。
体の中身が健康であれば、自動的に肌や髪もキレイになる。
これは僕も実際にその通りだと思います。
食事を変えるだけで皮膚炎が治ったという方や髪が増えたというかたは以前やった健康法講座でたくさん見てきたので。
現代医療が無視してきた体質とは?
西予医学のでは薬の効果を
「90%の人で症状の改善が見られた。一方、5%の人で副作用が見られた。」
というように表します。
つまり、確率で表します。
100%効果が出る、100%副作用が出ない薬は存在しないからです。
では、この効く人、効かない人、副作用の出る人、出ない人の差は何か?
現代医療の研究者たちも必死に原因を探っていますが、分かっているのはわずか歯科ありません。
一方、アーユルヴェーダでは薬(食事)を処方する時点で体質を考慮して処方します。
アーユルヴェーダの3つの体質(ドーシャ)
アーユルヴェーダでは体質(ドーシャ)を3つに分けます。
ほとんどの人は3つのドーシャのどれかに偏りやすくなっています。
これは魂から心と体が生じる時に決定すると考えられていて、生涯変わらないとされています。

体質というかエネルギーのようなもので、風・火・水・地のそれぞれのエネルギーがあって、どのエネルギーが過剰になりやすいか、不足しやすいかが生まれつき決まっていて、それを体質と呼んでいます。
- ヴァータ(風)
- ピッタ(火)
- カファ(地・水)
の3つです。
どれが良いというものではなく、それぞれのエネルギーのバランスが取れている状態が健康だとされています。
それぞれの体質について軽く解説すると
ヴァータ(風)
風のエネルギーなので、行動力を司っています。
なので、ヴァータの強い人はフットワークが軽いです。
一方、ヴァータが過剰になると落ち着きがなくなります。
興味がすぐに他のものに移るので、継続が苦手なタイプとも言えます。
体質としては、太りにくい、冷え性、乾燥肌などの特徴があります。
ピッタ(火)
火のエネルギーなので、情熱を司っています。
ピッタの強い人はリーダーとして人を率いるのに向いています。
一方、過剰になると怒りっぽくなったり、自分の価値観を人に押し付けるようになったりします。
体質としては中肉中背、暑がり、脂性肌などの特徴があります。
カファ(地・水)
大地のエネルギーなので、精神的に安定しています。
カファの強い人は何かをコツコツ継続するのが得意です。
一方、過剰になると動かざること地面の如しで、行動力がなくなります。
体質としては太りやすい、冷え性、色白などの特徴があります。
医食同源
アーユルヴェーダでは漢方と同じく
食事=治療
と考えます。
健康において食事が一番重要だと。
で、アーユルヴェーダでは特に消化力を重要視します。
消化がスムーズにできないと未消化物が消化管に溜まり毒(アーマ)になり、病気を引き起こすと言われています。
食後に眠くなるのも、消化がうまくできず、アーマが発生しているからだといいます。
消化がスムーズに行われていれば、食後に眠くなることはないです。
食の教えはワケわからないことも多い
食材には3つの体質のエネルギーを増加させたり、減少させたりする作用があるとされています。
科学的には何の根拠もないですが、直感的に分かるようなものも多いです。
具体例を挙げると、
レタスのような苦味のある葉野菜はヴァータを増加させ、カファを減少させるとされています。
また、トウガラシのような辛味の野菜はピッタを増加させます。

ちなみに僕は自己診断ではカファですが、カファの場合、水の性質が強くなりすぎるので、水を飲むことも良くないとされています。
水をたくさん飲む方が良いと言っている美容家的ポジションの人が多いですが、実は体質によっては水はダメです。
科学的にも水の代謝能力には個人差があることが分かっています。
代謝能力の低い人は水をたくさん飲むと水の処理で内蔵が疲れてしまいます。
あと、冷たい水は消化管の温度や体温を下げてしまうので、良くないです。
僕は飲み物は基本、白湯にしています。
アーユルヴェーダで白湯は3つのドーシャのエネルギーを整えるとされている万能の飲みもものです。

まとめ
アーユルヴェーダの教えの中にも科学的な説明がつくものが少なくない、のでそういったものは積極的に取り入れていくと良いと思います。
現時点でワケがわからない「ハチミツを金属と触れさせてはいけない」などの科学的に説明不可能なものは、できたらやる
というくらいのスタンスでいるのが良いのではないかと。
正直、食事については細かすぎるので、全て気にしていたら、神経症で発狂するかもしれません。
全5回で終了する予定だったのですが、アーユルヴェーダの話が長くなったので、終わりませんでした。
次回はアーユルヴェーダと波動の関係について書いて書いていく所存です。